第46回 愛宕薬師フォーラム令和7年3月13日 別院真福寺
紙とともに去りぬ ―怒り、煩悩との向き合い方―
講師:名古屋大学大学院情報学研究科教授 川合 伸幸 先生
はじめに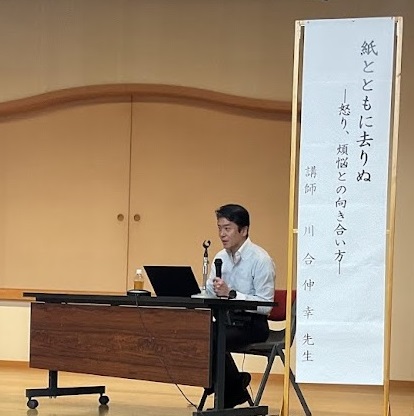
まず初めに、私たちの感情の発生頻度について考えてみたいと思います。アメリカで行われた一万人規模の調査では、約九割の人が一日のどの時間帯でも何かしらの感情を抱いていることがわかりました。最も多い感情は不安、続いて怒りや悲しみが多いことがわかりました。この結果から、私たちは日常生活の中で無意識に感情を抱いており、その中でも怒りや不安といったネガティブな感情が大きな割合を占めているのです。
また、調査した中で四割の人が、自分の感情をうまく制御できていないと感じていることがわかりました。今日のテーマである怒りを見てみると、約一割の人が常に何かしらに苛立っていることがわかります。怒りは自分を苦しめ、不快にさせます。また、怒りは相手を傷つけるということもあります。仏教でもお釈迦さまが「怒りの火は全てを焼き払ってしまう」と仰っているように、自己中心的な心から生じる怒りは自らを苦しめ、他人や周りへの思いやりが欠けた社会へとつながっていく、諸刃の剣といえるでしょう。
怒りの仕組み
人間の基本感情は〈喜び、悲しみ、怒り、驚き、恐れ、嫌悪〉の六つに大別されます。基本感情とは、人種や文化、年齢によらず同じように経験し、理解する感情をいいます。怒りは他の感情とは異なり他者や社会に向けられることが多いのが特徴です。自分に向けられる怒りの表情というのは脅威に繋がるので、他の基本感情より早く、生後四カ月ほどの赤ちゃんでも認識されると報告されています。次に神経科学の研究から怒りを引き起こす九つのきっかけを挙げます。
①生命や身体を守るとき
②侮辱されたとき
③愛する家族を守るとき
④自身の居場所を守るとき
⑤友人を守るとき
⑥社会の秩序を守るとき
⑦資源を守るとき
⑧自分の属する集団を守るとき
⑨自由に移動できないとき
この移動制限は物理的なものだけではなく、仕事が遅い同僚のせいで、仕事が進められないなど精神的なものも含まれます。これらの単語の頭文字を並べたLIFE MORTS(人生の致命傷)という状況において、多くの人は怒りを感じます。つまり、怒りとは自分や周りの者が脅威を与えられたときに対抗しようとする反応であり、怒りの感情表出は生存のために必要なものと考えられています。
怒るとどうなる
私たちは怒ったときに心拍や呼吸が早くなり、皮膚の表面温度や発汗量が上昇します。この自律神経の活性化に由来する変化は、原因となった相手に接近して攻撃できる状態、つまり戦闘態勢を意味します。当然怒りの状態が続いたり、回数が増えたりすると健康を害することになります。ストレスホルモンの一つであるコルチゾールの分泌が増え、心臓血管系に負担をかけるので、強い怒り後の心臓発作リスクは8.5倍といわれます。このような状態の変化は、中枢神経系の脳の活動にも現れます。
私たちは嫌悪や恐怖を感じると、右脳の前頭葉が活性化し、回避行動を取ります。逆に怒りを感じたときは、左脳の前頭葉が活性化し、戦闘態勢を取ります。この左脳の活性化は、赤ちゃんやおいしそうなものを見たときと同じ反応です。怒りの状態では、興奮や幸福と同様に、対象に「接近したい」という意識が生まれます。つまり、怒っているときには、体の状態を反映する自律神経系も、中枢神経系の脳も、共に相手に近づこうと反応することがわかります。
謝罪について
私たちは幼いころから「まず謝りなさい」と教育を受けてきました。とりわけ日本人はすぐに謝罪することで有名です。しかし「すみません」といった単純な謝罪は、それが自発的なものであれ、促されたものであれ、思っているほどの効果はありません。怒りの反応には接近の動機づけ(攻撃性)と不快感という二つの側面が存在しますが、謝罪によって相手の攻撃性を鎮める効果はありますが、不快感にはほとんど影響しないということが実験でわかりました。実際に謝罪を受けるよりも頭の中で謝ってもらったと想像した方が効果があったという実験結果まであります。
怒りと快感情
怒りには攻撃性という側面があると申しましたが、攻撃はしばしば快感情と関係します。
①仕返し:攻撃されたと感じたときに快感情を高めようとし、自身の肯定的なイメージを守ろうとするための攻撃
(例)解雇をいい渡された人が元雇用主の車のタイヤに穴をあける
②戦いに伴う高揚:暴力に関連した喜びを経験するために、対象を定めた攻撃行為をしたいとの本能的な欲求
(例)戦場で敵を撃ち殺したときに皆でよろこぶ
③日常の加虐性嗜好:意図的に苦痛を与えることから生じる喜び
(例)性被害者をバッシングする
④ざまぁみろ:他人の不幸は蜜の味
(例)応援しているボクシング選手が、敵をノックアウトした時に経験する興奮やスリル
このように、相手を攻撃したくないと思っていても、叩きのめしたいという気持ちがあります。私たちの体の仕組みがそうなっていると考えるしかありません。怒りや攻撃性中枢は、欲求(食欲や性欲など)と密接に関連していて、衝動性のスイッチは快感情と関連しているからです。男性の場合、攻撃性や嫌悪、不安、恐怖などの不快情動の調整に関わる脳の分界条床核と性的指向に関係する前視床下部間質核が女性より大きいという脳の特徴が見られます。
怒りの抑制方法―身体性認知―
認知科学の研究では、体の状態によって認知や感情が変化するということが報告されています。例えば表情を変えると感じ方が変わるということや上を向くと実際に気持ちが前向きになるということがあります。真言宗の教えでいえば三密行というのがこれに当たるのかもしれません。怒りの抑制ということで具体的なものを挙げれば、怒りは左脳と関係しているので、右脳を刺激するために左手を握ると怒りが抑制されます。私たちの実験では、単純な謝罪を受けるより、仰向けになるほうが、より怒りの攻撃性を抑制することがわかっています。また別の研究では、血糖値との関係もわかっています。私たちは怒りを理性で抑えようとして脳を働かせます。したがって、脳のエネルギー源であるグルコースを取り入れ血糖値を上げると、怒りの抑制効果があるということになります。
怒りの抑制方法―心理学的アプローチ―
まずは、注意をそらすという方法です。私たちは自動車メーカーのホンダと実験を行っていますが、怒りを感じながら運転すると非常にミスが多くなります。運転中のイライラを鎮める方法の一つとして、運転中に外部環境に注意を向けさせる音声(路面が凍結していますなど)を流すと怒りが減少することが確認されました。
次にこれまでの研究から、怒りを抑制する信頼性の高い手法をご紹介します。
①自己距離化
怒り体験を遠くから眺めるような想像を行います。例えば、自分の提案が否定された状況の会議を、上から眺めるようにイメージします。これは抑制効果が高く、他の感情を抑制したという知見も多くあります。一方で恥を伴う怒りは抑制できないことや、心的イメージの生成をうまくできない人も多いと報告されています。そこで複雑な過程を経ずに効果を得る方法として、第三者視点で自己距離化を行います。つまり、「私は腹を立てている」ではなく「(自分の名前)は腹を立てている」とすることで脳の活性を抑制することができます。また、違う時間の視点から自己距離化を行うことも有効です。心的時間旅行といいますが、タイムマシンで一年後に行き、今の怒りを考えてみるということも効果があります。
②再評価
中立的な立場から怒りの場面を解釈し直します。「自分が正しいとは限らない」といった立場で、相手の事情を想像します。この手法により感情を抑制するときに働く脳領域が活性化し、交感神経の活動を押さえるので、効果が最も高く現れます。しかし、相手との関係が悪いときは抑制できなかったり、手順の中に前述の①自己距離化が含まれるので、難しい方法ともいえます。
③祈る
腹が立った相手に対して、感謝の祈りを捧げると怒りが減少します。この方法では、腹が立った体験を肯定的に意味づけた人ほど、より怒りを鎮めることができ、さらに怒りが再燃しにくいという報告があります。
④腹が立ったことを書き出す
文章で記述しようとすると、客観的に状況を記述せざるを得ません。これも実験で怒りの身体反応が弱まるということがわかりました。
⑤紙に書いて捨てる
これは今日のテーマでもある、私たちのグループの研究結果です。物体は、自分自身の状態や思考を反映した情報源として利用され、情動や態度に影響を与えることがあります。例えば、自分の大切な日記を嫌いな人に触られると、凄く気持ちが悪く感じますが、その日記が消滅すると不快感も消えます。藁人形の呪いもそうです。藁人形が壊れると、呪いの対象となった人も壊れると考えます。この習性を利用し、「怒りを意味した物体の破棄で怒り体験から離れる」という新しい怒り抑制について検討しました。従来の手法の課題であった、イメージの難しさがなく、相対的に簡単な手法になります。「怒り」を感じた参加者に「ちくしょう」とか「むかつく」とかだけではなく、「どうしてそう思ったのか」という原因を紙に書いてもらい、三十秒ほど眺めた後、くしゃくしゃと丸めてゴミ箱に捨てます。すると書いて保持しただけのグループと比較して、有意に怒りが抑制されました。同様にシュレッダーにかけるという実験も行いました。こちらは怒りを感じる前のレベルまで、怒りが抑制されました。心理学的には投射といいますが、怒っていることを活字に表すと、そこに気持ちが乗り移り、捨てることでその気持ちも無くなるということが起きていると考えられます。
怒りはお釈迦さまの時代から御し難いものですが、人間に備わった生存に必要な機能です。しかし、怒りを制御できないと、自身の健康や社会に深刻な悪影響を及ぼします。怒りのメカニズムを理解し適切に制御することで、より健全な社会と人間関係を構築できるようになるのではないでしょうか。

